|
|||||||||||||||||||||||||||
|
今日、わが国は、内外でさまざまな問題に直面し、その解決のための処方箋を 明確に描けないまま、国民の多くは現状と将来に、大きな戸惑いと不安を抱いています。 政治不信の増大、経済の先行き不安、非正規型雇用の増大による不当な格差の拡大と生活基盤の劣化、社会保障制度への信頼の低下、東アジアをはじめとする不安定な世界情勢など、多くの問題が山積しています。 われわれは、この混迷する現状を打開し、希望の持てる将来を切り開くため、政策を提言し、その実現のため、「力」を一段と強化していくべきだと考えるに至りました。 そして、政策立案を担う学者・学識経験者が広く連携し、また、政策の推進・実現を担う「自由にして民主的な政治・労働・社会運動」の賛同者を幅広く結集し、新たな組織を構築することを決意しました。 一、新組織は、自由・公正・連帯の理念を基調とし、活動を展開していく。 一、自由で民主的な政治システムの擁護、充実を図る。 一、活力のある公正な経済社会の構築、発展を図る。 一、公正にして連帯溢れる社会システムの前進を図る。 一、自由と正義ある平和な国際社会を建設し、各国と連携して世界的規模での福祉増進を図る。 政策研究フォーラムは、五つの目的のため、理念・政策の研究と提言を行い、その成果を普及・実現するため教育・啓蒙活動を行うとともに、その理念・政策の実現をめざします。 また、中央に加えて地方にも活動拠点を設立し、全国的に活動を展開していくものであり、広く参加を呼びかけていきます。 政策研究フォーラム |
|||
| このページのtopへ戻る | |||
|
2016年5月13日改訂 政策研究フォーラム理事長 谷口 洋志 <基本的理念> わたしたちは、自由・公正・連帯の基本理念に立ち、政治、経済、社会、国際などの領域で改革の政策を提言し、推進していきます。 一、政治――自由で民主的な政治システムの擁護・充実 わたしたちは、自由で公正な民主的政治システムを実現し、それをさらに充実させるように活動します。 戦後、わが国はまがりなりにも民主的な政治体制を発展させてきましたが、残されている課題も少なくありません。 先進民主主義諸国のように、自由な民主的政治システムの維持・確立を信条とする勢力が社会に広く浸透しておらず、 この政治システムを確たるものにする精神的基盤を社会に確立できていません。 自由で公正な民主的政治システムを支える思想基盤を強固にするために、憲法、政治・行政、教育について論議を進め、政策開発をおこないます。 これを通じて、政権交代を可能にする政治を創出します。 さらに、政策開発能力の衰退、政治不信の蔓延、政治参加の停滞、政治的人材開発の低迷、政党政治の未成熟など、積年の政治課題も解決を見ていません。 自由な民主的政治システムを維持するという消極的な姿勢に終始せず、時代の課題に即応した、 高い問題解決能力を備えた自由で公正な民主的政治システムの構築をめざします。 二、経済――自由・公正・連帯を基盤とする持続可能な経済社会の構築と発展 わたしたちは、自由・公正・連帯の理念を基盤とし、現在世代だけでなく将来世代への影響にも配慮した持続可能な経済社会の実現をめざします。 市場経済では、経済・金融危機が繰り返され、そのたびに国民生活が犠牲にされてきました。 また、所得や富の一部への集中、不安定な雇用状態や劣悪な労働条件などによる「格差の問題」も生じています。 今後は、人工知能やロボットの利活用、あらゆるモノがインターネットにつながるIoT時代の到来などが引き起こす生活環境や雇用環境へのさまざまな影響も予想されます。 経済の持続可能性を高め、グローバル化・高齢化・人口減少・情報化に対応するために、 環境保全と資源・エネルギーの安定確保、生産性の向上と競争力の維持、海外市場への積極的進出、労働力の確保やシルバー人材の活用が要請されています。 わたしたちは、こうした時代の変化・要請に応えるために、自由・公正・連帯という価値に依拠しながら、 不公正な「格差の問題」を解消し、 「安心かつ安定した雇用環境」を整備し、資源・エネルギー・環境・人口・食糧などにおける「持続可能な経済社会」を構築することをめざします。 そして、現在世代の生活や状況を改善するだけでなく、豊かさと快適さという資産を将来世代に残すように努めます。 三、社会――連帯に基づく公正な社会システムの前進 わたしたちは、経済的繁栄を重視するとともに、社会の諸領域での機会均等や労働条件の改善等を図ることにより、その成果を公正に分配し、 人々の生活水準の向上の実現をめざします。 高齢化・人口減少が急速に進展する中で、持続可能な財政基盤の確立と、それに裏打ちされた社会保障制度の再構築は喫緊の政策課題です。 社会の変化に対応した人的資源の開発、雇用可能性を高める生涯教育(キャリア形成支援)、新しい労働市場政策など、早急に実現すべき課題も少なくありません。 また、ワーク・ライフ・バランスなど「労働生活の諸条件」を改善し、女性・高齢者・若者がその多様な資質や能力を伸ばし、活かすことができ、 格差や貧困が固定化されない社会を実現する政策や活動が求められています。 わたしたちは、これらの課題を国際社会と連帯しながら実現します。 四、国際――自由と正義ある平和な国際社会の建設、世界的規模での福祉の増進 わたしたちは、各国の協力により世界平和を確保するとともに、世界レベルの福祉の拡充を主張します。 世界の冷戦構造は、いまや終局を迎えようとしていますが、アジアでは未だ終結をみないでいます。 わたしたちは、平和憲法があるから平和が保たれているといった観念論に組みすることなく、現実的にわが国の安全を保障する途を求めてきました。 その努力を継続はしますが、それにとどまらず、自由と正義を基調とする、平和な国際社会の建設をめざします。そして、 そのための政策を提言し、主体的、積極的に推進します。 今日では、民族的・宗教的に不寛容な勢力による紛争が増大し、国際テロなど「新しい脅威」も生じています。 新しい国際環境の下、安定した国際システムの構築が求められており、わが国の貢献の道を確かなものにしていかなければなりません。 また、世界福祉の増進と途上国の自立支援のため、新しい政策と活動が求められています。 理念の乏しい援助政策に代わる、世界福祉を増進する政策が必要です。それとともに地球温暖化の防止など、地球環境の保護も重要です。 わたしたちは、そのための政策を提言し、それを実現すべく活動を展開します。 |
|||
| このページのtopへ戻る | |||
|
1.政研フォーラムは何をする組織か 政策立案を担う学者・学識経験者と広く連携し、自由・公正・連帯の基本理念に立ち、政治・経済・社会・国際などの領域で政策を研究・提言するとともに、地方に活動拠点を置き、教育・研修活動や連携活動を通じ、政策の推進や実現を目指します。  ≪具体的活動例≫ (1)会員が抱える産業・労働・社会政策などの研究と提言及び推進を図る。 研究委員会・・・労組連絡会構成組織・議員連絡会や関係団体からの要請に対応する研究活動。 (2)教育・啓蒙活動として、中央・地方での研修会などを実施する。 中央・・・全国会議、新世紀セミナー、政策懇談会など 地方・・・都道府県で年1回研修会を実施する (3)「改革者」、書籍、学習パンフレット、の出版。 (4)講演会、研修会などへの講師派遣。 (5)中央・地方における構成組織間の連携活動。 2.組織の構成 政研フォーラムは、理念や政策に賛同する次の個人会員及び団体会員で構成します。 (1)学者、学識経験者、労組役員OBなど (2)労働組合、企業など (3)各級議員 (4)その他、この組織の考えに賛同する個人 3.参加の形態 (1)団体会員(労組・企業・団体など) ・正会員・・・・労組連絡会の構成組織 ・賛助会員・・・上記以外の労組、企業、団体 (2)個人会員(理事・評議員・賛同者・各級議員) ・正会員・・・・理事、評議員 ・賛助会員・・・各級議員 (3)一般会員 ・・・「改革者」購読会員 4.組織体制 本部のもとに支部を設置し、支部のもとに都道府県連絡会を置き全国組織とする。 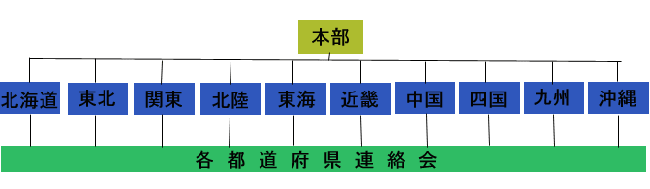 (1)支部 支部は、本部からの交付金で運営し、会議体は運営委員会とする。 ・都道府県連絡会で実施する研修会への支援と調整 ・都道府県連絡会との連携・調整及び構成組織間・地域の情報交換 ・本部との連携 ・その他 (2)都道府県連絡会 連絡会の運営で費用が発生する場合は分担金とし、会議体は幹事会とする。 ・支部と連携し研修会の「テーマ・講師」の選択 ①国の基本政策(安全保障、外交・防衛、教育、環境・エネルギー、社会保障など) ②民主的労働運動の理念と活動 ③自由・公正・連帯の理念と政策 ④政治・経済・社会の動向 ⑤その他 ・年1回以上の研修会の企画と参加者への募集展開及び実施 (年間1回研修会=2講座の費用は本部負担) ・構成組織相互の連携と協力及び構成組織間・地域の情報交換 ・政策推進に関し地域で合意できる活動の検討 5.組織運営 (1) 本部には「評議員会」「理事会」「常務理事会」を置く。 また、新組織を支援する労働組合が連携するための組織として「労組連絡会」、国会議員が連携するための「国会議員連絡会」を置く 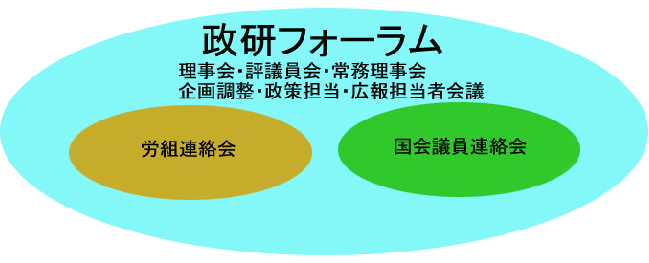 (2)労組連絡会の活動 1)政研フォーラムの諸活動への支援 ・諸事業(研修会)への積極的な参加 ・研究委員会への要請と対応 ・常務理事会との意見交換会・交流会の実施 ・「企画調整」「政策担当者」「広報担当者」会議に参画する ・地方組織(支部・都道府県連絡会)の運営に対する支援 ・その他必要事項 2) 構成組織相互の連携 ・各構成組織の政策課題に関する意見交換 ・政策提言項目の調整 ・政研フォーラムに対する研究・提言に関する要請 ・構成組織間の交流 ・その他必要事項 3) 国会議員連絡会との連携 ・政策提言項目の整理と研究・提言内容の精査 ・政策提言項目の政策推進活動 ・国会議員連絡会設置に対する支援 ・日常活動への支援・協力 ・その他必要事項 (3)国会議員連絡会の活動 1) 政研フォーラムと連携した活動 ・政策提言項目の整理・研究の要請 ・提言内容の研究と精査 ・常務理事会との意見交換会の実施 ・諸事業(研修会)積極的な参加 2) 国会議員相互の連携活動 ・政策提言の研究と研鑽 ・人間関係づくり 3) 労組連絡会との連携 ・各構成組織の政策課題について連携 ・政策提言の理解活動 ・人間関係づくり (4)諮問機関として、①企画調整会議 ②政策担当者会議 ③広報担当者会議を新設しました。 |
|||
| このページのtopへ戻る | |
| このページのtopへ戻る | |