 ・日 時:2025年2月17日(月)~18日(火) ・日 時:2025年2月17日(月)~18日(火)
 ・会 場:「砂防会館」(東京都千代田区平河町港区海岸2-7-4) ・会 場:「砂防会館」(東京都千代田区平河町港区海岸2-7-4)
 ・参加者:328名 ・参加者:328名
 総合テーマ「危機の克服」 総合テーマ「危機の克服」
 ☆多数ご参加いただき感謝申し上げます。 ☆多数ご参加いただき感謝申し上げます。
政策研究フォーラム2025年全国会議は、国内外の情勢が激動する中、われわれが今後進むべき方向性を
見定めるべく開催いたした。
2022年2月に始まったロシアのウクライナ侵攻は、いまだにその帰趨が判明していません。ウクライナの
防衛作戦は欧米諸国の支援で続けられていますが、支援の今後の見通しもはっきりとはわかりません。2023年
に始まったガザ侵攻も終わる見通しが立ちません。国際情勢は、急速に不安定化しつつありますが、その背後
にあるのはアメリカの覇権衰退です。
このような状況で、2024年の米大統領選挙では、トランプ氏が再選されました。第2次トランプ政権の
行方は予断を許しませんが、第1次トランプ政権の方向性、すなわち「アメリカ・ファースト」、アメリカの
国益が第1に重要であり、既存国際秩序の維持や同盟国を含む他国の利益はそれに比べて二義的な重要性しか
持たないという路線は、今後もさらに推進されると考えなければなりません。これまでの対外約束や既存の
政策路線もリセットされる可能性があります。こうした可能性を含み、日本の政策を立てていなければなり
ません。
世界経済は、インフレ懸念がやや沈静化し、堅実な成長への道程を歩みつつあります。日本経済はようやく、
緩いインフレと賃金上昇の好循環を歩み始めたばかりです。この動きを着実に持続させるための経済政策と、
労使の協力が必要です。日本の抱える多くの問題は、日本経済の低成長に起因しています。着実な成長を実現
できるよう、あらゆることをすべきです。
2025年全国会議は、「危機の克服」をテーマとして、基調講演と3つの部会を開催しました。
1日目の基調講演では、正念場を迎えている日本経済の今後の見通しを分析しました。労働者にとって
重要であるだけでなく、日本社会のすべてのことが経済成長にかかっているからです。
これに続き第1部会では、「政策合意と連立の行方 ―新しい政治をどうつくるか―」を論題にして、
2024年総選挙以後の自公連立政権と野党との関係の変化を踏まえて、政策課題にどう向き合うか、2025年夏
の参院選にどう取り組むかを議論しました。
2日目の第2部会では、「米トランプ政権に世界はどのように対応すべきか」を論題にして、アメリカ、
欧州、中国の専門家が議論しました。第2次トランプ政権が起こすと見られる大転換が米国や国際社会に与える
影響や求められる対応について、専門家の議論を通じて、事実と認識を共有しました。
第3部会では、「実質賃金引き上げには何が必要か」を論題に、賃金上昇を実質的な豊かさにどのように
つなげていくのかを、マクロ経済、税・社会保障、エネルギー政策などの切り口で議論しました。
基調講演と3つの部会の議論は、今後の日本の方向性を見定める羅針盤となるように構成いたしました。
参加者のみなさまが、全国会議の議論を踏まえて、労働組合が、組合員の意識と行動をよりよいものにして
いくための機会になりましたら幸甚に存じます。
|
第1日(2月17日・月曜日)
開会式 開会の辞 主催者挨拶 来賓祝辞 (12:30~13:00)
基調講演 「転換期における日本経済の展望」
(13:10~14:10)
政策研究フォーラム副理事長・青山学院大学教授 中村 まづる 氏
|




|

|
主催者挨拶:谷口 洋志 理事長
|
来賓:壬生 守也 電力総連会長
|
来賓:川合 孝典 参議院議員
|




|

|
基調講演:中村 まづる 副理事長
|
司会:永山 博之 常務理事
|
会場風景
|
|

|
第一部会 「政策合意と連立の行方ー新しい政治をどうつくるか」 (14:20~17:10
|

|
報告者 立憲民主党
立憲民主党 代表代行
|

|
長妻 昭 氏
|


|
|
第一部会の皆さん
|
|

|
〃 国民民主党 代表代行
|

|
古川 元久 氏
|

|
〃 産経新聞編集委員室長兼特任編集長
|

|
田北 真樹子 氏
|

|
司会者 宇都宮大学教授
|

|
中村 祐司 氏
|
|
|
|
|
長妻氏は、給与が物価を上回れば社会保障は解決する。労働生産性はヨーロッパ並みに上がっているのに日本だけ賃金が上がらないと述べた。古川氏は、政治に求めるのは目の前の生活をよくしてもらいたい。旧民主党の失敗は、目の前の生活に期待した国民に、政党としてやりたいことをやってしまったことと述べた。田北氏からは、選択的夫婦別姓より今の生活。国会が議論できるようになったことは良いこと。スキャンダルを予算委員会で議論する虚しさを国民がわかったとの見解を述べた。
|
|

|

|

|

|
| 報告者:長妻 昭 氏
|
報告者:古川 元久 氏
|
報告者:田北 真樹子 氏
|
司会者:中村 祐司 氏
|
|
第2日(2月18日・火曜日)
|

|
「米トランプ政権に世界はどのように対応すべきか」(9:30~12:10)
|

|
報告者 上智大学教授
|

|
前嶋 和弘 氏
|


|
|
第二部会の皆さん
|
|

|
〃 上智大学教授
|

|
河﨑 健 氏
|

|
〃 防衛研究所地域研究部
中国研究室専門研究員
|

|
五十嵐 隆幸 氏
|

|
司会者 中央大学名誉教授
|

|
谷口 洋志 氏
|
|
|
|
|
前嶋氏は冒頭、日本では大きな勘違いをしている向きがあるが、この選挙は「トランプの圧勝」では決してなかった。一般票はハリスと、わずか1.5ポイント差で21世紀では最も僅差と述べ、国際秩序を支えてきた国家主体の中心にあるアメリカの変質がますます顕著になっているため「グローバル・ガバナンス」という概念そのものがいま、大きな危機を迎えているとの見解を示した。河﨑氏は、トランプはヨーロッパが先送りしてきたこと、目をつぶってきたもの、ヨーロッパにどういうことができるのかを突いていると述べた。五十嵐氏は、トランプは予測不能と言われるが、第1次政権の政策の延長線上で考察できる。習近平はバイデンより、やりやすいのではないか。こぶしは振り上げるがテーブルの下では手を握る。日本はうまく立ち回らないといけない。そこにかかっていると述べた。
|
|

|

|

|

|
| 報告者:前嶋 和弘 氏
|
報告者:河﨑 健 氏
|
報告者:五十嵐 隆幸 氏
|
司会者:谷口 洋志 氏
|
|

|
第三部会 「質賃金引き上げには何が必要か」 (13:10~15:50)
|

|
報告者 中央大学教授
|

|
川崎 一泰 氏
|


|
|
第三部会の皆さん
|
|

|
〃 常葉大学名誉教授
国際環境経済研究所副理事長兼所長
|

|
山本 隆三 氏
|

|
〃 上智大学教授
|

|
丸山 桂 氏
|

|
司会者 青山学院大学教授
|

|
中村 まづる 氏
|
|
|
|
|
川崎氏は、物価上昇の抑制を目指すのではなく、それを超える賃上げが必要。成長しないと豊かになれない。これまでとれていなかった料金をきちんととるだけでも生産性は上がると述べた。山本氏は、物価上昇の原因は、化石燃料価格の上昇だ。エネルギー価格の変動は人件費の上昇以上の影響を経営に与える。日本経済は、脱炭素のスピードを緩めても、競争力ある安定電源を確保しAI、半導体製造などの産業を育成する必要があると述べた。丸山氏は社会全体の社会保障費を縮小することは難しく、可処分所得の引き上げのために税・社会保障で何ができるか、複雑な税制や社会保障制度を理解することが必要。近視眼的な個人にどのように理解を訴えるかが課題と述べた。
|
|

|
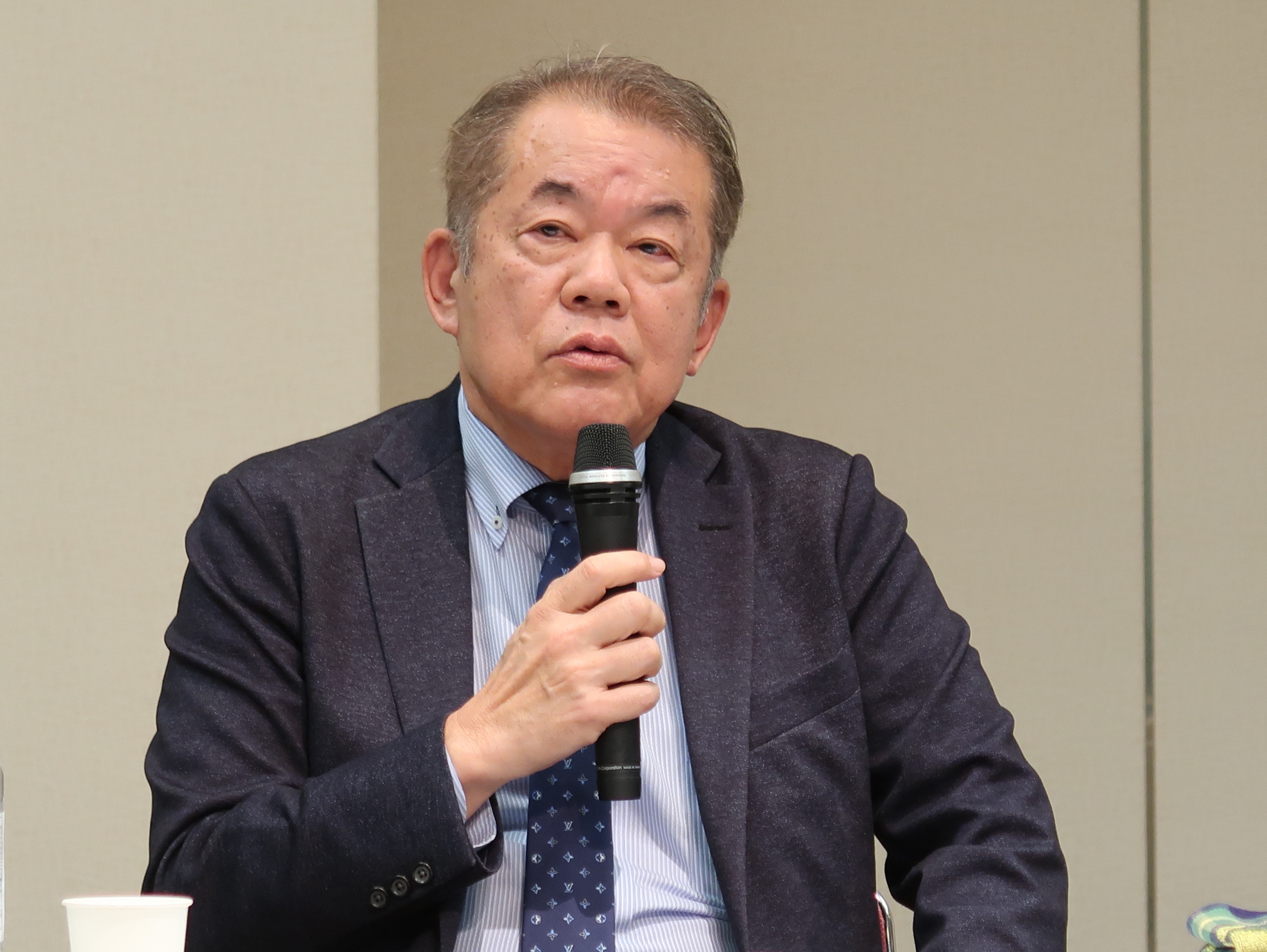
|

|

|
| 報告者:川崎 一泰 氏
|
報告者:山本 隆三 氏
|
報告者:丸山 桂 氏
|
司会者:中村 まづる 氏
|
|
|
☆「2025年全国会議」の詳細は会員誌「改革者」4月号・5月号に掲載されます。
|

|